もう、何もかも上昇している感じですね。
当ブログを書いている2025年9月末ですが、
いよいよペットボトルも1本200円時代です。
日経株価は、45,000円超え
地金価格は、20,000円/g超え
この2つはバブル時代を超えています。
最低賃金も2025年度は全都道府県1,000円超え!
今、景気が良い感じがしますか?
因みに、バブル時代の電気代を調べてみると
1980年(昭和55年)の電気料金は28.36円/kwh
というデータがありました。
これが通常期なのか夏季料金なのか平均なのか分かりませんが、
電気料金よりかなり高いのが分かります。
当時は、エアコンの普及も進んでいなかったため
電気請求額はさほどだったのかもしれませんね。
少し、話題が逸れますが、中小企業白書を見ると以下の通りのデータがあります。
損益分岐点比率:大企業47.9%、小規模企業83.6% 差が拡大傾向
労働分配率:大企業51.2%、小規模企業84.6%
何を言いたいかといいますと、
中規模企業、小規模企業は、様々なコスト上昇や人件費上昇への対応が
厳しいというのが分かります。
更に、某自動車メーカーは、部品メーカー各社に価格の値下げ要求とか!?
乾いた雑巾を…
本来の方向に戻します。
今年は、梅雨が短く、
6月以降酷暑が続きましたが、
それでもやはり彼岸に入ると気候が落ち着いてきた感じです。
10月に入ると、そろそろエアコンの冷房運転も終わりになるかもしれません。
エアコンの冷房運転は、室内機内に結露を発生させます。
10月も日中はまだまだ暑い
この状況で急に運転を止めると、お風呂を出たあとの浴室内に近い環境になります。
そのままだとどうなりますか?
そう、カビ発生!
そして暖房運転で放出!!
そうならないために、冷房運転が終わりにする場合は、
乾燥運転をするのがおススメです。
さて、いよいよ本題に戻ります。
毎月月末に大手電力会社各社から公表される燃料費調整。
これが毎月の<電気料金変動の大きな要因>です。
これで、使用量が同じだとしても毎月電気代が変わってきます。
その他、そもそもの単価が変動することがありますが、これは稀です。
基本料金設定がある契約もありますが、
使用量が全く同じであっても変動するものコレ「従量料金単価」です。
当ブログでは電力量料金(=使用量単価+燃料費調整単価+再エネ賦課金)としています。
使った量に応じて課金されるものです。
毎月月末に電力各社から翌々月検針時(翌月使用分)の燃料費調整単価が発表されます。
前述の通り、ほぼ毎月変動しますので、定点観測でその推移をみています。
前段が長くなりましたが、まず中部電力から見てみます。
2025年10月度使用分(11月検針分)中部電力電力量料金推移
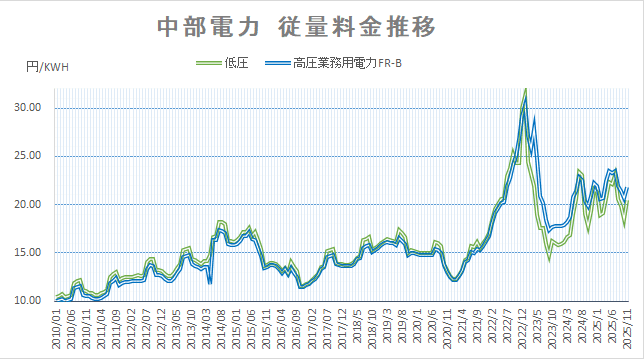
前年比では、高圧104.5%、低圧105.8%
約5%高くなっています。
前月比では、高圧105.7%、低圧110.5%
エアコンの中間期ですが、ベースアップという感じですね。
2025年10月度使用分(11月検針分)沖縄電力電力量料金推移
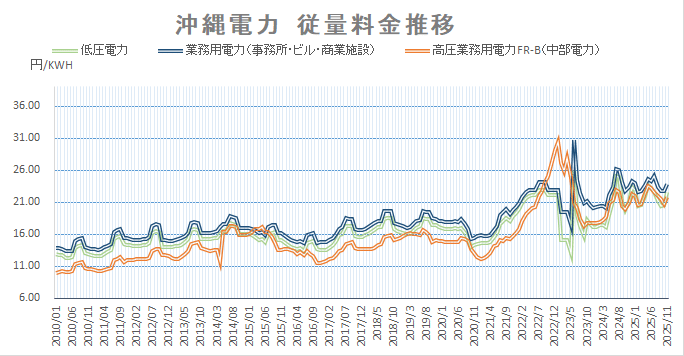
他社同様、2024年以降は、支援の有無によって変動が大きくなっていました。
前年比では、高圧101・5%、低圧106.4%
低圧が約6%高くなっています。
ビルや商業施設などで利用される高圧業務用で、中部電力と比較をしていますが、
かなりその差がなくなってきました。
108.7%となっています。
コメントはしませんが、
実は、料金改定された2023年以降、燃料費調整単価が10円以上マイナスが続いています。
省エネはコスト
少しくらい、省エネ・節電を行っても追いつきはしませんが、それでもやらないより良い
無理な省エネ推進は、我慢を強いられることから反発が起こることもありますが、人が我慢しない省エネ対策って興味ありませんか?
電力単価が上がっている分、対策にかかる費用の投資回収期間も縮まりますね。
同じ10%削減でも額にすると大きいということになります。
使用量の変動要素が大きいものは何でしょうか?
夏に対策をとると、引っ越しなどと同様、関係各所の繁忙期となり、対策費用も増加してしまう可能性があります。
まだ、やっていない対策はあるのではないでしょうか?
ご確認下さい。
2025年は中小企業も環境力向上は必須|省エネ診断・省エネチェックリストでまずは現状把握から~省エネ推進のはじめの一歩~
業務用エアコン、冷凍機の省エネ、暑さ対策のことなら
当社株式会社i-Mage.まで、お気軽にお問い合わせください
i-Mage.ブログ【Vol.0528】でした。
